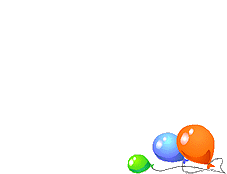スタンリー・キューブリック ※ 下に フルメタル・ジャケットUPしてあります。ドラックして下さい。
題名=シャイニング 1980年 (アメリカ)
原作=スティーブン・キング 出演者=ジャック・ニコルソン/シェリー・デュヴァルetc...
スティーブン・キングの原作ものって、映像にすると、ビックリするほど陳腐になる事が多いというのは結構言われてますが、主に、それはTVドラマがヒドイ
え〜〜〜?こんなんなん?みたいな・・・
特に「IT」なんかあんまりといえばあんまりなオチにガッカリしたという記憶があります。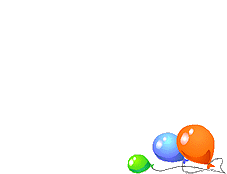
B級狙いで撮ってるんでしょうが・・・
「IT」っだって、ラストがなけりゃ、結構面白かったのに・・・でも、B級狙いならこれでいいのか
しかし、「スタンド・バイ・ミー」とこの「シャイニング」は違いました
シャイニングの終わり方は原作の方が好きなのですが、それを差し引いても完成度も芸術性もすんばらしい
でも、キングは当初からこのキューブリックの撮った「シャイニング」に不満を持っていて、後になって自ら撮り直したんですよね・・・(TVドラマとして)
それを観ると、申し訳ないのですが、格の違いが歴然なんだけどな・・・B級狙いだからしょうがないか・・・
原作者としてのキングは大好きなんだけど
まぁ、目指している方向がまったく違うのだから、比べてみてもしょうがないのね・・・
おそらく、キューブリックは余計だと思うものを、枝を掃うかのように切っていったんだと思うんです
ただ、この枝の部分こそ、いかにもキングといったエピソードが満載だった訳でして
・・・・・立腹するでしょうね
でも、結果的にはキューブリックの方が荘厳な恐さでして・・・なんとも気味が悪い
ジャック先生が笑えるという意見もありますが、それを差し引いても十分恐いし不気味です
気が変になっていく人間を表現させたらキューブリック天下一品だし
この物語の中には、幻覚とか幻聴とかではない、明らかに霊というものが出てくる設定になってて
その霊がかなり気持ち悪いんですよね〜
バスタブに浸かってブヨブヨになって腐敗している初老の女性とか、(←これは鳥肌ものです)
父親に斧だかライフルだかで惨殺された双子の女の子たちとか、(←シャイニングという特殊な能力を持つ息子の所に出現します〜一緒に遊びましょう〜って)
それなのにそれなのに、一番恐いのはジャック・ニコルソン演じる主人公だったりして
それを助長する妻ウィンディの超神経質なビクビクぶり!感染しますよ〜
なぜなら、ここで実際に殺人を実行できるのは、生きた人間だけなんです
それが、どうやらここの霊達と波長が合ってしまっているという恐怖。
主人公は主人公であると同時にオーバールック・ホテルの忌まわしい過去の亡霊でもある訳です
何回もしつこいんですけど、たった1箇所原作通りにして欲しかったと思うのはラストなんですよね・・・
だって、ハロウィンさん大好きなんだもん♪
この映画を私に教えてくれた友人はドク(息子)がホテルの廊下で遊んでいる時に、どこからともなくボール転がってくる場面で、次のカットの時、絨毯の柄が逆方向になっていると教えてくてました。
2005/11/11UP
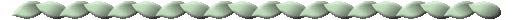

スタンリー・キューブリック
題名=フルメタル・ジャケット 1987年(アメリカ)
原作&共同脚本=グスタフ・ハスフォード 原題=ザ・シヨート‐タイマーズ(短期除隊兵)
出演=マシュー・モディン/ヴィンセント・ドノフリオ/アダム・ホールドウィンetc...
作者、グスタフ・ハスフォードは、主人公ジョーカー(ニックネーム)と同じく、海兵隊所属の報道員として、ベトナムを転戦したという経歴の持ち主です。
ベトナム戦争とは、戦死者4万6千人、事故死者1万人、戦傷者30万人、戦費1400億ドル(米国防総省発表)を費やした、アメリカ介入型の戦争であります。
1965年に、当時のアメリカ大統領ジョンソンによって発表された『偉大な社会』という政策の一環だったのでしょうか?歴史に疎い管理人は、未だに、なぜベトナム戦争にアメリカが介入したのかが、よく判りません。
映画では二部構成になっているのですが、小説では三部構成でした。
ここは、一応映画のお部屋なので、映画の構成で話を進めて行きます。
第一部の訓練所でのやりとりは、やはり字幕が大幅に変更されていました。
それでも、蛆虫、糞虫、当たり前の会話がバンバン飛び交っていたような気が・・・。(^^;)
「右手にム○コを握り、左手にライフル持って、これが自分のライフル、これが銃、一つは戦闘のため、一つは遊びのため、ティーンエイジャーの女王なんて欲しくない、M-14ライフルさえあれば満足さ」(小説の中の一節より)
訓練所=生き残る為の洗脳機関なんだと感じました。
そんな中で次第に緊張してゆく兵士予備軍達・・・
しかし、パイル二等兵(←ニックネーム本名レナード・プラット)だけが、失敗、甘えを繰り返すのでした。
事あるごとに、ガーハイム軍曹にいじめられていたレナードでしたが、いつまでたってもレナードの顔には甘えたようなニタニタ笑いが消えません。・・・(癖?)
ある時から軍曹はレナードの失敗の責任をレナード以外の小隊全員に課すようになります。
それでも、レナードはヘマをやり続けてしまいます。
ある晩、『毛布パーティ』(小説より)と称した制裁がレナードに加えられました。
それは、百人の新兵が見守る中、毛布をかけて身動き取れない状態にされたレナードのビールっ腹を、各班の班長達が、タオルに石鹸を包んで打ちまくるというものでした。・・・仲間だと・・・庇ってくれていると信じていたジョーカーも・・・
「レナードの悲鳴は遥か彼方で聞こえる病んだロバの鳴き声に似ている。」(小説より)
その翌日から、レナードの顔からニタニタ笑いが消えたのでした。(ほぼ、完全にイカレたのか・・・)
それからレナードは、自分のライフルとのみ会話するようになっていきます。
映画、第一部のラストは、レナードが自分のライフルにフルメタル・ジャケット(完全被甲弾)を装着して、ガーハイム軍曹を撃ち殺し、次いで自分も同じライフルで自殺するというところで終わります。
このシーンから第二部への場面の切りかえがナイスでした!
切りかわった場面はベトナムなんですが、一般の地区のようで、なんだか緊迫感もなく、ホッとしました・・・
私はどうやら、こういった「一張一弛」のタイミングの上手い監督に弱いみたいです。(^^;)アラン・パーカーしかり
二部では、ベトナム戦争の壮絶さ、悲惨さ、虚しさが描かれていきます。
後半に登場するべト●ンの姿無き無数のスナイパーによって、標的にされ殺されてゆくジョーカー達・・・
面白がって、いたぶる様な攻撃が、正体を知るまでは、凄腕の敵のスナイパーが、余裕で遊ぶように攻撃している姿を想像させていたんですが、その正体は、たった一人のベト●ン女性でした・・・。
容赦なく執拗に攻撃していたのは、極限の恐怖からだったのでしょうか・・・
ラストに歌うミッキーマウスのマーチがまた皮肉が利いていて、映画の内容とは別に「上手いなぁっ!」と思ってしまいました。
そして、この主人公等の感情に対する、演出の客観的突き放し方が、
却ってリアリティを生み出しているという凄さ!
キューブリックってやっぱし天才なんだ〜!o(≧▽≦)o
そして、1975年終戦。
北ベトナムの兵士も南ベトナムの兵士もアメリカの兵士も・・・地を這う虫となり、あの緑の地獄で殺しあった・・・。
それは既に、お国の為ではなく、・・・友を助ける為に、自分を守る為に、殺しあった・・・。
ベトナム戦争ってなんだったんでしょうか・・・
ベトナム戦争を描いた映画は数あれど、そのの中から1本選べと言われたら、私は迷う事無くこの「フルメタルジャケット」を選びます!
2006/01/06UP